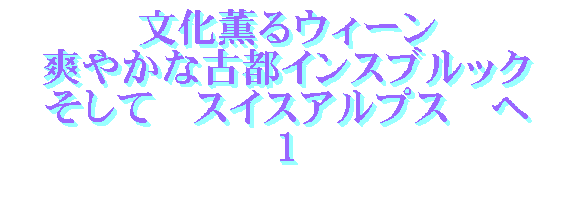ドナウの至宝 Wien
息子の妻の専門とする学問分野は、ウィーン(ヨーロッパ中世・近世)の歴史であり文化である。手もとに広瀬佳一編著になる「ウィーン・オーストリアを知るための50章」という本がある。この本の執筆者の一人が彼女である。私は今回の旅にあたってこの本を読んで事前学習をした。
ウィーンは最盛期には「日の没することなき帝国」とまで言われたハプスブルク帝国の首都である。そこではシェーンブルン宮殿のような華麗な建築が次々に生み出され、モーツァルトをはじめとする豊かな文化・芸術が育まれた。ハプスブルク家の領地はオーストリアはもちろんのこと、ボヘミア、ハンガリー、チェコスロヴァキア、イタリア、ポルトガル、スペイン、さらには南アメリカなどにまで及んでいたという。それは主に婚姻を直接の契機とするものである。15世紀以来、神聖ローマ皇帝位もハプスブルク家によってほとんど独占されるようになった。
ウィーンはまたドイツを中心とするドイツ語を話すゲルマン民族東進の拠点、最先端の都市でもある。オーストリアの皇太子が暗殺されたことに端を発する第一次世界大戦は、ハプスブルク家帝国の崩壊とオーストリア共和国の誕生をもたらした。
また第三帝国と称したナチ・ドイツに組み込まれたオーストリア(オーストリアはヒトラーを生み出した国でもある)は、第二次世界大戦に巻き込まれていった。そして、ウィーン・オーストリアは第二次大戦後に連合国によって分割占領された後、永世中立を条件として主権を回復した。やがて永世中立のステータスは、厳しい東西対立が続いた冷戦期において、ウィーン・オーストリアの国際的地位を大いに押し上げた。
しかし、EU(欧州連合)に加盟し、ユーロを使用する国となった現在は・・・
6月12日
画像は シュテファン大聖堂の内部
ノイヤーマルクト
市民公園(後ろにグリルパルツァーの像・さらに後ろに自然史博物館が見える。)
美術史博物館(ルーベンスの絵の前で)
終日、ウィーンの主に旧市街地を歩いた。
ギリシャ教会 グリーヘンバイスル
ハイリゲンクロイツァーホーフ 白地に赤い縁取りの旗が掲げてあるところが見所だという。息子は一々丁寧に説明してくれるがあまりに多くて覚えきれない。
シェーンラテルンガッセ
ゾンネンフェルスガッセ などという細い通りを歩く。花が活けてあったり、馬に乗るための石が埋め込まれていたり。通りの向こうには大学教会も見えた。ウィーンの町でも最も古い壁画というのも見た。やがて
シュテファン大聖堂
「ウィーンの象徴」「ウィーンの魂」といわれる寺院。天を突くように聳える高さ137mの塔に目を奪われる。12世紀から造成が始まったこの寺院の中で、現存で最古のものは正面入口の門。13世紀後期ロマネスクのもの。全体の外観はゴシック様式で、内部の祭壇はバロック様式だそうだ。フィアカーといわれる観光辻馬車がたくさん停まっていた。
ノイヤーマルクト 建物に囲まれたこの広場にはたくさんの像が置かれていた。
カプツィーナ教会(皇帝納骨所)は、ハプスブルク家の墓所である。
アルベルティーナ この文書館は息子の妻が足しげく通うところだそうだ。
ウィーン国立オペラ座 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏を聞いたり、オペラに魅せられた息子が鑑賞のためしばしば訪れるウィーン。オペラ座にも何度も来たことがあるそうだ。オペラの中心であったイタリアにちなんで、ヴェネツィア式ルネッサンス様式の外観はヨーロッパ三大オペラ劇場にふさわしく壮大でかつまた華麗。
ゲーテ広場を通り、ブルク公園を抜けていくと、モーツァルト像があった。一緒に記念撮影。公園を出たところが新王宮の裏であった。表に回る。とにかく広い。ブルク門を入ると、オイゲン公騎馬像とカール大公騎馬像が向かい合って立っている。王宮は、民族学博物館、狩猟・武器部門と古楽器コレクションのエフェンス博物館、世界一美しい図書館といわれる国立図書館プルンクザール(ここも息子の妻の仕事場の一つ)、王宮宝物館、王宮礼拝堂などに使われている。ヘルデンブラッツ英雄広場からは、フォルクス庭園を通して、国会議事堂や市庁舎の建物や高い塔が望める。
市民公園に入ると、色とりどりのバラが今を盛りと咲いている。自分でもバラをたくさん育てている息子はこの時期ここを訪れるのははじめてだとたいへん喜んでいた。バラの中にグリルパルツァーの像があり、その向こうに自然史博物館の建物が見えていた。反対側は宮廷劇場。公園を出て、白いギリシャ神殿を思わせる民主主義の象徴としてその発祥の地アテネにちなんで構想されたという国会議事堂の前を通り、宮廷劇場(プルク劇場)の正面に出る。ヨーロッパの中でも一流中の一流といわれている劇場だ。いわゆるなまりのない美しいドイツ語でいろいろな演劇が上演される。リンクを挟んで向かいが市庁舎。教会でもないのに100m以上の尖塔を造るのはけしからんという抗議にあい、設計者のF・フォン・シュミットは塔自体は98mに抑え、さらにその上に市庁舎の男Rathausmannという騎士像(3.4m)を載せ、手には6mの旗を持たせて計107mの高さにしたという逸話がある。
さらに進むと息子の妻も留学していたヨーロッパの名門国立ウィーン大学。リンクの向こうには市壁の址も残っていた。
ここでひとまず旧市街地の散策を終え、リンクの上を走る路面電車に乗って戻ることにした。美術史博物館を見学するためである。見たい博物館等場所はたくさんあるのだがなにしろ日数が限られているため今日はここに絞ったのである。威厳に満ちた存在感のあるマリア・テレジアの像が聳え立つ広場の東西に対称形の堂々とした建物が建つ。自然史博物館と美術史博物館である。ウィーンで美術館を一つだけ見るなら迷わずここへ。パリのルーブル、マドリッドのプラドと並んで世界三大美術館だけに時間はたっぷりかけて鑑賞したいと案内書にでていた。入ってまず驚かされるのが、柱、置かれた彫像など建物そのものがすでに芸術。3時間あまりをかけて絵画を鑑賞してまわった。ハブスブルクの巨大な財力を持って収蔵された美術品の数々はその質量ともに圧倒され息をのむばかりであった。息子はブリューゲルのコレクション、ラファエロなどの作品がことにお気に入りの様子であったが、夫はルーベンスのたくさんの絵の前から動こうとしなかった。
名残を惜しみつつ美術史博物館を出てシュテファン大聖堂に戻った。聖堂の前に05と刻印したものが残っていた。これはOS(オーストリア)と書くべきところナチの目を逃れるべく05と書き、オーストリアへの熱き想いを主張したのだという。大聖堂の中へも入ったが彫刻、ステンドグラスのなんともすばらしい聖堂であった。
その後、フィアカー(観光辻馬車)に乗って60分コースを回った。少し高い視点でまだ歩かなかった小路などを通り街を見るのもまた楽しかった。ウィーンで2番目に古いペーター教会やヨーゼフ広場、スペイン乗馬学校、ミヒャエル広場などを馬車の上から見た。
ウィーンは、石畳の道、石を積み上げた城壁、石造りの建造物、まさに石・石・石の石(シュタイン)の文化の街であった。いつの時代も外敵と戦い自らを守らなければならなかった人々にとっての石の文化・・・私は美しい、すばらしいが、そこにめっぽうな強さといささかの頑なさを感じたように思った。
|